
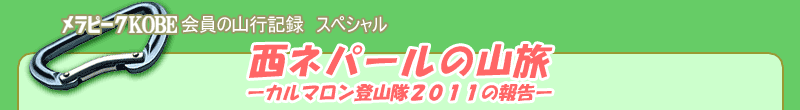 |
 ▲ベースキャンプ 背後の山は6022m峰  ▲コジ・ラ下の湖 コジ・ラ(5495m)付近に6159m峰のHCを設置すべく向かう。テント場からは右岸沿いに歩く。流れに忠実に行くと徒渉が困難となるため。北西方向からの尾根にあがって高まきする。大きな岩が重なり合う急斜面を登り、岩壁は右にトラバース。そこから下りると再びコジ・コーラの5100m付近に出る。流れは広く分散して水深は浅くなっている。徒渉してガレ場を登っていくと右下(南)に湖が見える。この湖畔にテント設営の跡と標竹を発見した。おそらく2007年にコジ・カンに挑戦したイギリス隊のものだろう。かれらは南西から試登した。湖を見ながらガレ場を登るとラプツェ(積み石塚)がある。ここから傾斜のきつい斜面が続き6159m直下の壁のすそにたどりつく。この壁下をトラバースするが足元がくずれやすく不安定だ。トラバースが終わるとコジ・ラの氷河上に着く。  ▲コジ・ラの朝 HCは氷河右岸から6159m峰に続く斜面下の平らな場所に設営した。ここから6159m峰やコジ・カンは見えないが、東と南の山の眺めが良い。6000m級の無名峰が五つ以上見えるが登られているのは一つだけだ。コジ・コーラに滞在してあちこちの山に登ったりチベット側の湖を訪ねたりしたら楽しいだろう。コジ・ラはその昔、チベットとの行き来に使われたようだ。今はチベットへの道は通行しやすいナムジャ・ラに移行したためこの峠はほとんど使われていない。チベットから朝日が昇り山々が赤く染まるのに見とれてしまう。この5400mに泊まっても特に高度障害の症状はなく、あとは天気を祈るのみである。  ▲6159m峰への登路 翌早朝はガスで視界が100mほどだったが出発することにした。こんな天気なのでサーダーは、今日は行かないと思っていたようだ。「隊長のテントで物音がして話し声がし始めたので行くのだと思いました」と語っていた。HCから南斜面のガレ場にとりつく。広い斜面に出て雪田となるが、雪のないところをたどる。5700mから固定ロープが始まり登高器による登攀となる。アイゼンも装着する。東方向のチベットには、雲の晴れ間が少しばかりあり、湖が見えていた。さらに傾斜45度の斜面を登っていくと平らな雪上に出る。ここは頂上の南東にある前衛峰の東直下(5950m)である。ここで先行するルート工作を待った。またも45度の斜面を行くと雪庇がこちらに張り出しているところを乗り越える。そこからしばらく行くと三つ目の45度の斜面があり、ルート工作を待つ。その斜面を登ると西にあがる頂上稜線に出た。  ▲雪庇が頂上だった そこを頂上方向に歩き始めると雲が晴れ始めた。それまで視界がほとんどなかったのに頂上ではほぼ360度の展望が得られた。今までの連日のような悪天候は、今日の登頂をお膳立てするためであったかのように。隊員の喜びははじけた。頂上は東に張り出す雪庇となっている。西側の斜面に集合して写真を撮る。1997年の大阪山の会隊に次ぐ第二登である。コジ・カンは北西にあるが頂上付近は雲があり姿を見せてくれなかった。ただ予定した登攀ルートはある程度見えた。その取り付きに至る氷河歩きにも時間がかかるように思えた。頂上からBCがはるかな下にゴマ粒のように小さく見えた。この頃BCでは、登頂を遠望したコックのパダムが、われわれの無事帰還を祈るため祭壇で香木を燃やしていたのである。  ▲6022m峰のハイキャンプ 主目標はコジ・カン(6516m)であったが、それを断念することにした。BC到着後はまる1日晴れる日はなく、天気が悪い日が続いている。この状態ではBCから遠くに位置していて、C2以上の建設も予想されるコジ・カンを期間内に登るのは困難である。それで6022m峰に転進することにした。この山はコジ・コーラ左岸にあり対岸のBCからよく望める。正面壁は大規模なブロックの崩壊が見られた。それはすさまじく氷河の様相が大きく変わってしまった。注意深く観察した結果、ルートは頂上から北に落ちる氷河にとることにした。頂上の岩部分が困難であれば雪の斜面を反対側にトラバースするようハイポーターに伝えた。BCからコジ・コーラを渡渉してサイドモレーンの尾根上をたどり5100m付近で氷河に下りる。氷河は上から運ばれた岩と土砂をかぶっているが氷の露出もあり歩きにくい。HCは5450mに設置した。  ▲6022m峰の登路 夜半に雪となりテントは白くなった。朝になると雪はやんだが雲が多い。ハイポーター達はまだ寝ているのでテントに近づいて出発することを伝える。サーダーの顔には「またしてもこんな天気で登るの?」と書いてある。それでも出発して、しばらく行くと50度近い斜面があり固定ロープを使用して登るとヒドゥン・クレバスがあった。いったん傾斜はゆるくなるが、また45度の斜面があり上部に行くにしたがって斜度はゆるやかになる。この頃から、上部のガスが薄くなった。そしてS水の歩みが極端に遅くなった。疲労が激しいようだ。このまま登り続けるのは危険と判断し下山を指示した。5800mでハイポーター1名をつけてHCまで下山させた。本人はここから下山することを納得していなかったのであるがやむをえない。  ▲6022m峰の頂上にて |
| 大スラブに感動! 涙の宮崎クライミング |
 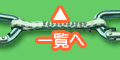  |
小豆島・親指岳クライミング |
Copyright(c) 2009- MERAPEAK-KOBE All Rights Reserved.